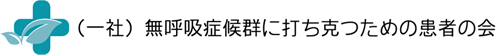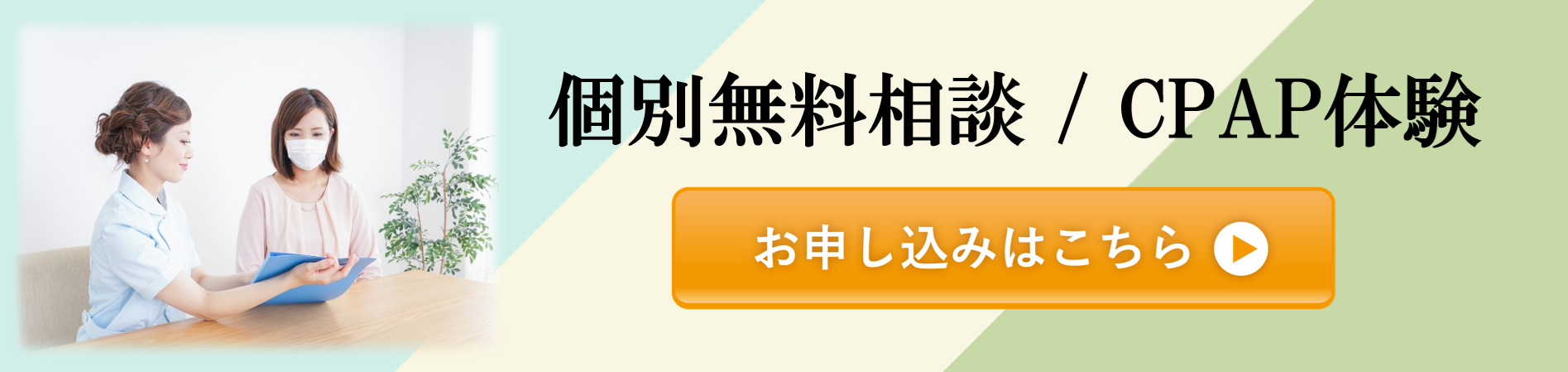睡眠時無呼吸症候群とは ― いびきの陰にある病気を、正しく知る

夜ぐっすり眠ったはずなのに、朝からだるい。
会議や運転中に、どうしても強い眠気が襲ってくる。
家族からは「いびきが大きい」「呼吸が止まっていた」と心配される――。
こうしたサインの背景に、睡眠時無呼吸症候群(SAS) が潜んでいることがあります。
SASは、睡眠中に繰り返し呼吸が止まったり浅くなったりすることで体内の酸素が不足し、脳や心臓、代謝系に負担がかかる病気です。自覚症状に乏しく本人が気づかないうちに進行する点が特徴です。
病気のしくみとタイプ
無呼吸は、主に上気道(のど)が狭くなり空気の通り道が一時的に塞がる閉塞性によって起こります。
解剖学的な要因(扁桃肥大、顎の形、舌の落ち込み)に加え、体重増加や飲酒、仰向け寝、鼻炎など日常的な因子も影響します。呼吸中枢の働きによる中枢性、両者が混在する混合性もありますが、成人では閉塞性が大半を占めます。
いびきは単なる「音」ではなく、気道が狭くなっているサインです。
放置のリスク
SASを放置すると、高血圧、心不全、心筋梗塞、脳卒中、糖代謝異常などの合併症リスクが上がることが知られています。夜間の酸素低下と覚醒反応(何度も浅く起きる状態)が自律神経を乱し、血圧や心拍に負担をかけるからです。
睡眠の質低下は日中の眠気、集中力低下、記憶力の低下、抑うつ傾向にもつながり、学業・仕事・家庭生活のあらゆる場面に影響します。運転や高所作業など安全が求められる場面では、事故リスクの上昇という社会的な課題にも直結します。
どんな症状が目安になるか
代表的なのは大きないびき、家族などの無呼吸のきづき、起床時の頭痛、口渇、熟睡感の欠如、日中の強い眠気です。夜間に何度もトイレに起きる、寝汗をかく、朝の血圧が高いなども関連が疑われます。
もっとも重要なのは「家族・同居人からの指摘」。
本人の自覚が乏しい病気だからこそ、周囲の気づきが早期発見につながります。
検査と診断の流れ
まずは問診と簡易検査(自宅で指先や鼻にセンサーを装着し、呼吸や酸素飽和度を測定)。
最近のスマートウォッチには、酸素飽和度などを測定できる機種も出ていますので、まずはそれらで試してみるのもお勧めです。
問診票はこちらから無料で入手することができます。
それらの結果で無呼吸症候群であることが疑われる場合には、医療機関で本格的な終夜睡眠ポリグラフ検査に進み、睡眠段階や呼吸、いびき、酸素、心電図、体位などを総合的に評価します。AHI(無呼吸低呼吸指数)が診断や重症度の目安になり、治療方針の決定に用いられます。
主な治療法
CPAP(シーパップ)療法は標準的な治療です。鼻マスクから一定の圧力で空気を送り、気道の閉塞を防ぎます。適切に使用できれば日中の眠気軽減、血圧改善、睡眠の質向上が期待できます。CPAPにも複数のメーカーがあり機能も異なりますので、CPAPに適応しにくい方には、自分に合うものを探すことも重要です。
自分に合うCPAPをお探しの方へ

CPAPの実機を試してみてください!
CPAP以外の治療法として、下顎を前方に保持して上気道を広げる口腔内装置(マウスピース)が選択肢になります。解剖学的な要因が強い場合や合併症に応じ、外科的治療が検討されることもあります。
どのような治療法がフィットするかは人によって異なりますので、CPAPが合わない場合でも、他のCPAPや他の治療法など、諦めずに、いろいろと試して頂ければと思います。もちろん、体重管理、禁酒・節酒、就寝前の過度な飲食を避ける、横向き寝の工夫、鼻炎対策、規則正しい睡眠習慣などの生活改善も非常に重要となります。
軽症~中等症の場合
ただし軽症~中等症と診断された場合は、CPAPが処方されません。
ということは、軽症~中等症でも眠気のリスクを感じていたり、頭痛などの症状が出ていたりしても、保険適用でのCPAPのレンタルができません。
この点を私たち患者の会では大きな課題と考えており、一つの対策として、メーカーならびに専門医の協力を得てCPAPの自費購入ができるようにしていますので、ご興味のある方は、ご相談いただければと思います。
CPAPを自費購入したいなら

続けられる治療のために
治療は「始める」こと以上に「続ける」ことが大切です。
CPAPであれば、マスクのサイズ・形状調整、装着時の違和感や乾燥への対策、圧設定の最適化、機器の衛生管理など、小さな課題を一つずつ解消していくことで継続率が高まります。
ひとりで悩むより、医療者に早めに相談し、同じ治療を行う仲間の知恵を借りるほうが近道です。私たちの患者会にも、「最初の2週間をどう乗り切るか」「旅行や出張での持ち運び」「職場への理解の求め方」「花粉症での対策」など、多くの実践知が集まっています。
家族・職場とのコミュニケーション
SASは周囲の理解で改善が加速する病気です。いびきや機器の音に配慮しつつ、病気の仕組みや治療の意義を共有すると協力が得やすくなります。
運転や深夜勤務のある職場では、適切な治療により安全性とパフォーマンスを高められることを、エビデンスベースで説明するのが有効です。偏見や恥ずかしさから受診が遅れる方もいるため、「眠気は努力不足ではなく病気のサイン」というメッセージを周囲に広げることが重要です。
患者会の役割
私たち「睡眠時無呼吸症候群に打ち克つための患者の会」は、正確な情報の提供、体験の共有、治療継続の支援、医療機関や関連団体との橋渡しを行う民間の患者コミュニティです。当事者と家族が安心して学び、相談し、実践できる場づくりを目指しています。初めてSASを知った方にも、長年治療を続けている方にも、それぞれの段階で寄り添えるヒントがあります。
はじめの一歩
「自分は大丈夫だろう」と先延ばしにせず、気づいたときが受診のタイミングです。まずは簡易検査からで構いません。生活を少しずつ整え、必要に応じてCPAPや口腔内装置を取り入れれば、翌朝の目覚めや日中の集中は変わっていきます。
ひとりで抱え込まず、信頼できる情報と仲間の支えを味方に、健康な睡眠を取り戻しましょう。
患者目線で役立つ最新情報を知りたい方へ
30秒で簡単登録!
ブログ記事やイベントなどの最新情報を無料でメール通知いたします。